近年、T2*, SWI, QSMに関する問題が出題されています。本記事では問題をまじえて まとめて解説していきたいと思います。(問題はJMRTS 認定試験過去問より引用)
T2*, SWIとは?
T2*WI, SWIとはどちらも、磁化率の差を強調した画像になります。SWI>T2*の関係にあります。
SWIとQSMの違いは?
SWIは磁化率強調像を定性的に得る撮像法、QSMは磁化率を定量的に算出した画像になります。
QSMは、T2*WIやSWIでは判別が難しい軽微な磁化率の差を描出することができます。例えばQSMでは、脳出血と石灰化を鑑別することができます。
第15回 問題13
正しい記述はどれか。3つ選べ。
- SWI は位相画像にローパスフィルターを施す。
- Synthetic MRI は脂肪抑制画像を取得することができる。
- フーリエ変換は deep learning によって置換することができる。
- MR fingerprinting では撮像パラメータを撮像毎にランダムに設定する。
- CEST (chemical exchange saturation transfer) MRI は MT(magnetization transfer)効果を利用している。
解説
ローパスフィルター→ ハイパスフィルター(低周波成分除去)- 正しい
置換することができる→ 置換できない- 正しい
- 正しい
第19回 問題18
T2*強調像について正しいのはどれか。2 つ選べ。
1. 磁化率効果は静磁場強度に比例しない。
2. TEを延長することで磁化率効果は小さくなる。
3. 過去に発症した脳内における無症候性微小出血の検出に優れる。
4. 局所的な磁場不均一による磁化率差を強調した撮像法である。
5. SWIは位相画像にフィルター処理を加えて高周波成分の除去を行う。
解説
比例しない→ 比例する小さく→ 大きく TEが長いとエコー形成前に位相分散し、磁化率効果が強調される- 正しい
- 正しい
高周波成分→ 低周波成分 ハイパスフィルター=低周波成分の除去
第18回 問題9
SWI について正しいのはどれか。
1. 流速による位相シフトの影響を受けやすい。
2. 強度画像を用いて石灰化と出血の鑑別ができる。
3. 位相画像に対しローパスフィルタを用いて補正する。
4. 位相マスクは位相の正負のずれに基づいて作成される。
5. T2*強調画像より磁化率の変化による位相ズレの感度が低い。
解説
受けやすい→ 補正している. (3軸のflow compensation)強度画像→ 位相画像から算出するQSMローパスフィルタ→ ハイパスフィルタ- 正しい
低い→ 高い
フィルターまとめ
SWI は位相画像にハイパスフィルターを施す
→ 低周波成分を除去するため
NEMA 均一性の評価:9点ローパスフィルタを使用
→ 高周波ノイズの除去を行うため
第20回 問題26
1. 動脈系の描出に適している。
2. 磁化率による位相差の違いを強調している。
3. 最小値投影画像では石灰化と出血の鑑別ができる。
4. 血流の位相分散を促進させるために流速補正は使用しない。
5. 微量な鉄沈着やデオキシヘモグロビン量の違いを描出できる
解説
動脈系→ 静脈系- 正しい
最小値投影画像→ 位相画像から算出するQSM促進させるために流速補正は使用しない→ 血流の位相分散を抑制するために 3軸に流速補正をかけている- 正しい
第13回 問題45
1. 動脈系の描出に適している。
2. 磁化率による周波数分散の違いを強調している。
3. 静磁場強度は低いほうが微細な磁化率の違いを捉えやすい。
4. ボクセルサイズは小さいほうが微細な磁化率の違いを捉えやすい。
5. 微量な鉄沈着や酸素飽和度(デオキシヘモグロビン量)の違いを描出できる。
解説
動脈系→ 静脈系周波数分散→ 位相分散低いほう→ 高いほう- 正しい →薄いスライスで高い空間分解能で、ボクセルが小さい方が微細な磁化率の違いを捉えやすい
- 正しい
第17回 問題17
- H-MR spectroscopy では悪性腫瘍のコリンピークが低下する。
- SWI において静脈は位相変化が少ないため高信号に描出される。
- Driven equilibrium(DE)パルスは T2 強調や脂肪抑制に使われる。
- 位相コントラスト画像は Qp/Qs(肺循環体循環血流比)を測定できる。
- BOLD 法では相対的にオキシヘモグロビンが低下するため信号が上昇する。
解説
低下する→ 上昇する少ないため高信号→ 大きいため低信号- 正しい
- 正しい
オキシヘモグロビンが低下する→ オキシヘモグロビンが上昇する
第15回 問題2
- 基底核や視床は灰白質である。
- 下垂体は血液脳関門が存在する。
- 脳の髄鞘化は2歳までにすべて完了する。
- 高濃度酸素を投与していると SWI(susceptibility-weighted imaging)で静脈を過大評価することがある。
- 高濃度酸素を投与していると FLAIR(fluid-attenuated inversion-recovery)で脳溝が高信号になることがある。
解説
- 正しい
- 間違い BBBが存在しないもの:下垂体, 脈絡叢, 松果体, 硬膜
すべて髄鞘化完成の目安年齢:2歳過大評価→ 過小評価- 正しい
第13回 問題23
1. CISS(constructive interference in steady state)は動きに強い。
2. ASL(arterial spin labeling)で算出できるのは局所血流量である。
3. Dixon 法にて((In-phase) – (Opposed-phase))/2 を計算すると水画像が得られる。
4. Balanced SSFP(steady-state free precession)の信号強度はT1/ T2 に比例する。
5. SWI(susceptibility weighted image)で Gd 系造影剤を用いると細い静脈が見えやすくなる。
解説
強い→ 弱い DESSS, CISSもbalanced SSFPと同様の信号強度を示すが「動きに弱い」- 正しい
水画像→ ((水+脂肪)ー(水ー脂肪画像)) /2 = 脂肪画像T1/ T2→ T2/ T1- 正しい
第17回 問題38
正しいものを選べ.
DWIBS:diffusion weighted whole body imaging with background body signal suppression,QSM:quantitative susceptibilitymapping,SWI:susceptibilityweightedimaging,CEST:chemicalexchangesaturationtransfer
- DWIBS は全身の拡散強調背景抑制法である.
- QSM は脂肪有率を定量的に算出した画像である.
- SWI は磁化率強調像を定量的に得る撮像法である.
- Computed DWI は 2 つ以上の b 値を利用して任意の ADC 値を求める手法である.
- CEST イメージングは脂肪と水のプロトン間での交換が起こる現象を示した画像である.
解説
- 正しい
脂肪含有率→ 磁化率定量的→ 定性的ADC値→ b値脂肪と水→ 異なる周波数にある2つのプロトンプール間
第19回 問題10
QSMについて正しいのはどれか。2つ選べ。
- 計測値は温度に依存しない。
- Multi echoでの収集が必要である。
- 鉄沈着と石灰化で計測値が異なる。
- ミエリンは常磁性体として検出される。
- 3D撮像に比べて2D撮像は測定精度が高い。
解説
依存しない→ 依存する- 正しい
- 正しい
常磁性体→ 反磁性体2D撮像→ 2D撮像はない
QSMまとめ
- 磁化率変化を定量解析した画像.
- MRIの位相画像から局所の磁化率を算出し、マップ化する手法.
- 3D-GRE法を使用.
- 強度画像と位相画像をMulti echoで撮像する.
- 位相画像から位相折り返し除去した全体磁場マップを作成する.
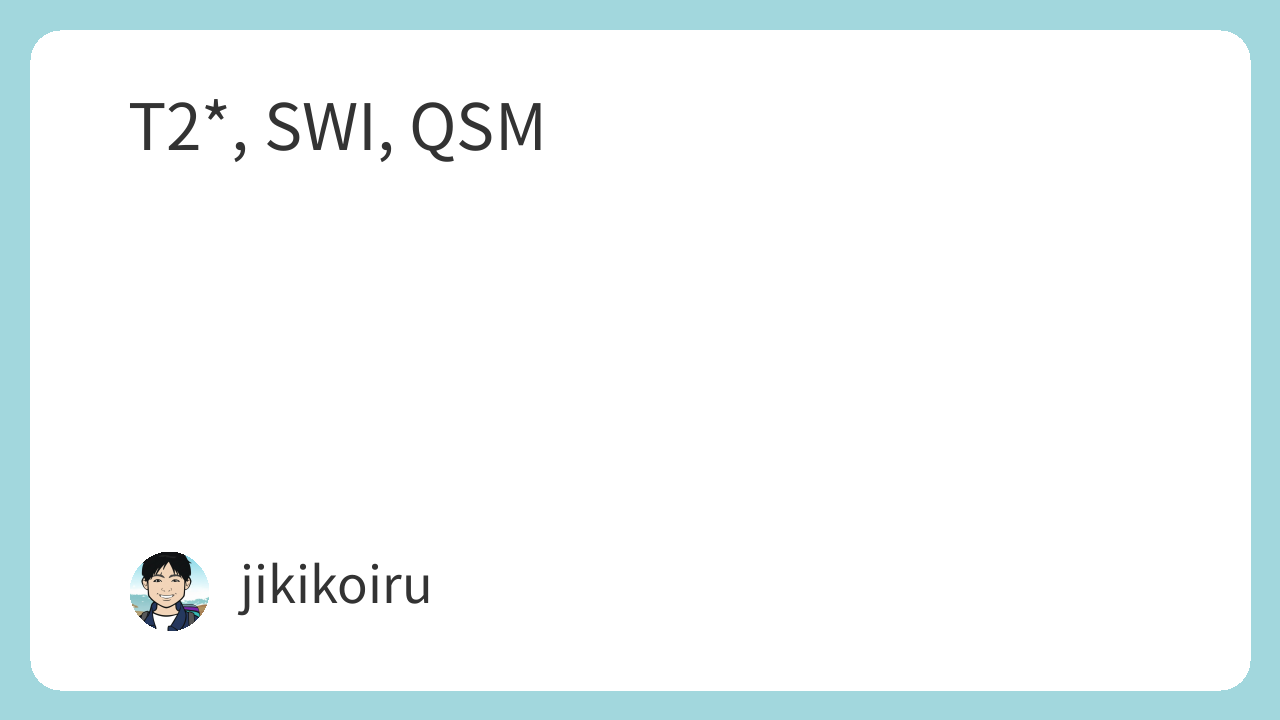
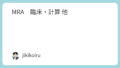
コメント